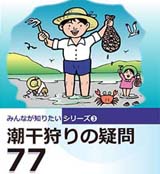[540] 投稿日付: 2002年 05月 26日 20:56
名 前: まてまて
e-mail :
タイトル: マテガイ大漁
初めて書き込みします。
5月26日に兵庫県の新舞子にある管理潮干狩り場に行って来ました、今回なぜかアサリが少ししかとれず(他の人は結構とってました)マテガイの5センチ以上のものが50弱とれました、最初は塩を使ってたのですが、沖の方で30センチぐらい掘るとすぐに手に当たり、手ぼりでいくらでもとれる感じでした夫婦2人、一時間半ほどで小さなものを含めると80ぐらいは取れました。
[539] 投稿日付: 2002年 05月 25日 20:23
名 前: あさりちゃん
e-mail :
タイトル: 黄金はまぐりは、、
木更津の方のいくつかの海岸でやっているイベントの
ようですよ。
見つけると海苔が商品として頂けるようです。
明日、見つけに行ってきまーす!
[538] 投稿日付: 2002年 05月 25日 00:00
名 前: ミソル
e-mail :
タイトル: ハタミ貝について
潮干狩り大好きで、行ったときは4時間は掘り続けるので翌日は必ず筋肉痛です。
数年前に、静岡県浜岡町にハタミ貝がいると聞いて、採りにいってみたことがあります。大きなものは採れなかったのですが、小さいのはいくつかいました。
現地のラーン屋さんで見せてもらったハタミ貝は、幅が11cmくらいあって大迫力でした。でも首まで海につかって採るみたいで素人には危険だと思われました。
だけどいつか大きいのを採ってみたいです!
[537] 投稿日付: 2002年 05月 24日 00:41
名 前: ゆみっち★
e-mail :
タイトル: 黄金ハマグリ!
皆さん初めまして!
「黄金ハマグリ」という言葉を
耳にしたことがあるのですがいったい
どういうものなのでしょう?
千葉にある潮干狩り場でのイベントか
何かなのですか?情報お願いします★
[536] 投稿日付: 2002年 05月 18日 18:25
名 前: カガミガイ超人
e-mail :
タイトル: 教えて下さい。
蛤大王様、ご無沙汰しております。
今年は、九十九里には行かず、ちょっと遠征してハタミなる物の謎がとけました。 私自身もちょっとすっきりしました。 後で、よく考えてみると私も九十九里で見た記憶がありました。 その時は蛤大王様と同じ様に特大の”アサリ”だと思っていました。
所で、九十九里でカイマキ(ジョレン)を使って良い(漁業組合が管理していない)浜等はあるのでしょうか?
ご存知でしたら教えて下さい。
[535] 投稿日付: 2002年 05月 17日 02:22
名 前: なおなお
e-mail :
タイトル: おしえてください。
はじめてカキコさせていただきます。
みなさん すごいですね!!
今度、浜名湖の周辺で潮干狩りに挑戦してみたいと思ってますが、詳しい場所など教えていただけないでしょうか?
また、ちょっとしたコツ等もありましたら一緒に教えていただけたらと思います。
よろしくお願いいたします。
[534] 投稿日付: 2002年 05月 16日 19:31
名 前: 山内千登世
e-mail :
タイトル: 行ってきました。
超人のお膝元の八景島海浜公園に初めて行って来ました。いつもは木更津の潮干狩り場なのでホント笑っちゃうぐらいとれませんでした。あらためて超人のすごさを感じた一日でした。
[533] 投稿日付: 2002年 05月 14日 22:40
名 前: ボーズ逃れ
e-mail :
タイトル: アサリ大漁
千葉県は三番瀬の浦安側で潮干狩りしてきました。
掘り果?は、
あさり:5リットルバッカン満タン
潮吹き:網満タン
マテガイ:一本
青柳 :6個
赤貝 :1個
潮吹きはここの情報のおかげで砂抜き完璧!
佃煮にしたので暫く楽しめそうです。
詳しい場所などを知りたい人は密かに教えますよ。
[532] 投稿日付: 2002年 05月 14日 20:55
名 前: 浜栗
e-mail :
タイトル: はまぐりの間引き(潮干狩り)
鹿島灘はまぐり(別名、チョウセンハマグリ)の間引き。
チョウセンハマグリ資源に及ぼす遊漁者の間引き圧力について(つまり潮干狩り)
要約]
2mmサイズ人工種苗の汀線域放流によって生き残ったチョウセンハマグリ稚貝が殻長15mm以上に成長した段階で、遊漁者の潮干狩りによってその大部分が間引かれていることから、遊漁者の間引き圧力を推定した。
茨城県水産試験場・浅海増殖部
[連絡先] 029-265-7452
[推進会議] 東北ブロック水産業関係研究試験推進会議
[専門] 増養殖技術
[対象] ハマグリ
[分類] 調査
背景・ねらい]
2mmサイズのハマグリ(チョウセンハマグリ)人工種苗を半閉鎖的水域の汀線域へ放流(平成10年3ヶ所、平成11年3ヶ所へ放流)したところ、放流から約1年後の生残率が6~56%であった。しかし、殻長15mm以降になると生残率が急激に低下し、放流から約2年後には生残率が0~5%にまで低下してしまうことが明らかとなった。
殻長15mm以降の急激な生残率の低下原因の一つとして、遊漁者の潮干狩による間引きが考えられたので、実際に遊漁者が潮干狩りによって間引く数量を定量的に明らかにするための調査を実施した。
[成果の内容・特徴]
平成10年及び平成11年放流群(xxxxx海岸)の生残率及び平均殻長の推移を示した。
平成10年、11年放流群とも殻長15mm以降に生残率が急激に低下し、放流から2年後に生残率が平成10年放流群は2%、11年放流群は1%まで低下した。
人工種苗の生残が良好なxxxxx海岸(突堤などの人工構築物に囲まれた約1kmの汀線域)において平成12年4~5月、平成13年4~5月の2回、それぞれ連休を夾んで2週間の間隔を開けて遊漁者による間引き数量を推定した。
その結果、平成12年の調査では現存量(3月13日現在62万個)の27%、平成13年の調査では現存量(3月28日現在23万個)の32%がそれぞれ間引かれていることが明らかとなった。
なお、その間の推定遊漁者数(聞き取りから推定)は、平成12年、平成13年ともに延べ300人前後と推定された。
サイズ別の減少率をみると、平成12年の調査では殻長20mm以上、平成13年の調査では殻長15mm以上の稚貝が選択的に間引かれ、殻長15mm以下の稚貝はほとんど間引かれていないことが明らかとなった。
なお、水試職員が実験的に徒手採捕を行ったところ、1m2当たり100個以上の密度でハマグリ稚貝が分布している場合、1時間当たり500個程度採捕できることが明らかとなった。
[成果の活用面・留意点]
ハマグリは殻長30mm前後になると自ら粘液紐を出して沖合へ移動すると考えられているが、殻長15mm以上になると遊漁者に大量に間引かれることが明らかとなったことから、遊漁者に間引かれる前に、沖合へ移植することが可能かどうか、移植に適したサイズ・時期・場所及び汀線域での効率的な回収方法・回収コストなどについて早急に検討する必要がある。また、遊漁者に実態をPRして、はまぐり資源の維持管理に理解を促す方策を立てるために活用する。研究課題名:二枚貝増殖技術開発研究から 抜粋
30mm以上つまり 80mmぐらいのはまぐりは、沖合いに生息している。
[531] 投稿日付: 2002年 05月 14日 09:00
名 前: 蛤大王
e-mail :
タイトル: 長年の謎が今ここに・・・
「珍しい貝知ってる貝」を読みました。
今まで悩み続けてきた謎が、本日解けました。九十九里浜で蛤を採っていると、時々蛤とは明らかに違う平べったい貝が採れていました。貝の形からアサリの巨大化したものとばかり思っていました。九十九里は大自然が一杯だからアサリの成長も早いんだと思っていました。しかし、なんとハタミ貝と言うんですねえ。こいつは、砂抜きをしていると、ものすごく水管が長く気持ち悪いやつだなあと見ておりましたが味の方はすごくイケていましたよ。
これで今後安心して貝採りが出来ます。皆さんの行動力に感謝いたします。