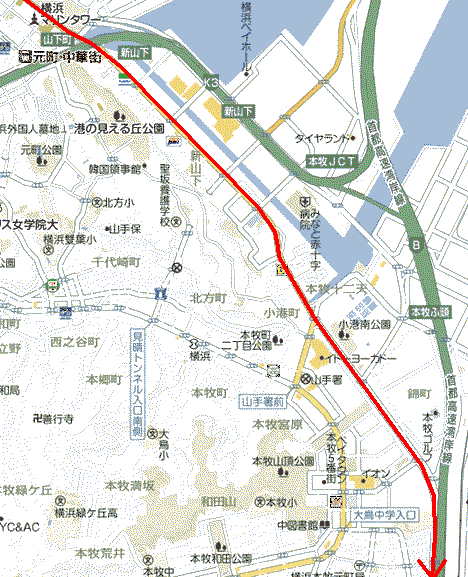小港橋の交差点。大きな通りが斜めに交差している。

小港橋交差点を過ぎたところに中部水再生センターがある。センターの前面に明治時代の下水道の遺構が展示してある。庭の中に入れるのか入れないのか、遺構を見せたいのか見せたくないのか微妙な展示なのだが、生垣の外から肉眼で解説を読むのは不可能なので書き写すことにした。かつて汚水を流していたとはいえさすがは石、100年以上の時を経ても時代の波に洗われて美しく気品も増しているようだ。
明治時代の下水道

横浜の近代下水道は、明治2年から4年にかけて館内外国人居住地(現在の中区山下町)を中心に、お雇い外国人R.H.ブラントン(英国人、1841~1901)が陶管により主に雨水排除を目的にした下水道整備を行ったのが始まりです。
その後、明治10年代のコレラ大流行と居住地人口の激増に対応するため、神奈川県は明治14年から20年にかけて居住地で下水道の改修工事と居住地周辺で近代的な下水道整備を全国に先駆けて築造しています。
この石造り暗きょは、昭和62年に中区海岸通りで発掘されたもので、施設年度は明治14年頃と推定されます。

この暗きょは明治10年、12年のコレラ大流行の防疫対策として、明治14年から建設が始められたときに敷設されたものです。
文明開化の時代は、お雇い外国人技師が各地で各種近代技術を移植、導入していました。この時期、神奈川県土木課御用掛三田善太郎は、日本人の手によりわが国で最初の近代下水道を設計施工しました。
この石造り馬蹄型暗きょは、日本人街において整備したもので、関内外国人居住地のレンガ製卵形管とほぼ同じ時期に築造されたものです。
昭和62年に中区馬車道で発掘されたものです。

この暗きょは明治17年に当時の外人居住地であった関内山下町付近にれんが造り暗きょ約四キロメートル汚水ます40個を築造したといわれるものの一部である。これは当時わが国における近代式水道の模範といわれ最も古いもので昭和34年にシルクセンター付近で発掘された。
卵型の断面は流量の変化が大きい場合に低水事にも相当の流速を持たせて汚物の堆積を防ぐことができる合理的なものでれんが積みで化学作用に強い材料を使っている現在では施工が困難なので使われていない。
中部水再生センター解説板より

ここからしばらくは首都高速湾岸線の下を走ることになる。