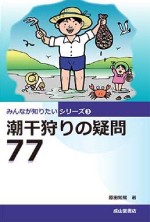しじみの漁獲量の変遷
図14は1965年(昭和40年)から1992年(平成4年)まで28年間の主要生産地のしじみ漁獲虚の推移をあらわしたものです。
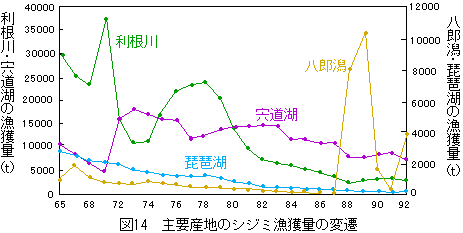
河川の中で虚も独獲豊の大さい利根川は、河口より四〇キロ上流まで海水が流入し、昔からじみ漁獲量第一位の産地でした。特に、1970年は3万8000トンも漁獲され、全国の漁獲量の約80%を占めていました。ところが昭和46年になると、河口より18.5キロ付近に河口堰が完成し、それより上流域では海水の流人が遮断され塩分が入らなくなりました。また、河口堰より下流域ではしじみには塩分濃度が濃すぎる状態になり、同時に水の滞留や酸素不足によるしじみの大量斃死(へいし)という事件が起こりました。
これ以降、一時的な資源の回復はありましたが、現在では3,000トンまで漁獲量が激減し、この水域のしじみ資源は失われつつあります。これと同じような状況が長良川でもおきたのはいうまでもないことです。
次いで、八郎潟は干拓前は日本で一番大きい汽水潮でヤマトシジミの漁獲量もかなりありました。1957年(昭和32年)からはじまった干拓事業で約70%が乾陸化され、残りの水域は調整池として淡水化されました。事業が完成した1964年以降は年毎に漁獲量が減少しました。しかし、87年に台風の影響により、語整池に海水が入りヤマトシジミが大量に発生し、88年8260トン、89年1万750トンもの漁獲量を記録したわけです。しかし、90年には1700トン、91年には47トンまで激減しました。八郎潟ではヤマトシジミが繁殖するために必要な適度な塩分が維持されないためと予想されますが、このままではいずれ消滅する可能性が強いと思われます。
琵琶湖では1965年以降に、水質悪化と乱獲のためセタシジミの漁獲量が減少しています。特に、1979年以降の減少は激しく、現在では200トンと1965年当時の漁獲の10分の1以下になっています。
今後のしじみ漁業
しじみの漁獲量の変遷でもわかるように、現在ではヤマトシジミの主要な産地は宍道湖だけといっても過言でないように思います。この湖のヤマトシジミは、水産資源として大変重要な位置を占めるようになったわけです。この宍道湖においても、中海・宍道潮の干拓淡水化事業により中海北部が干拓地堰堤で仕切られた1975年(昭和49年)ごろから、中浦水門を境にして中瀬の環境が大きく変化したといわれています。この影響によるものかどうかはわかりませんが、宍道湖のヤマトシジミの漁獲量がこのからやや減少してい
るような気がします。
いずれにしろ1965年以降主要なしじみ生産地の漁獲量は単なる生産調整の範囲を越えて、毎年減少しているようです。1990年以降中国からのしじみの輸入が急増し、1994年には一万トン以上輸入され宍道湖の生産量より多いのが窮状です。
しじみは湖沼や河川の砂底質の酸素が豊富な浅いところに生息しています。しじみたちは移動能力があまりないので、自分たちで最適な生息場所をみつけることができない動物です。じっと我慢して周りの環境が回復するのを待つ動物です。しかし、我慢の限界を越す環境変化が起こるとしじみたちは生きていけなくなるのです。このような動物にとって何よりも生息地の環境が重要であり、しじみたちが繁殖できるような生態系の維持・改善が琵琶湖や宍道湖などにもとめられるでしょう。
しじみ漁業にかぎらず、農林水産業は21世紀の日本ばかりでなく、世界にとって食糧の確保などの面で極めて重要な産業です。とかく資源がなくなれば、稚魚を放流するとか種苗生産を行うなど、結果がはやくわかる眼前の改善を行いがちです。しかし、生物が生息できる環境、ヒトといろいろな生物が共存できる環境の維持・改善こそが、今後のしじみ漁業、そればかりか、今後の世界の食糧生産にも重要であることをヒトは理解しなければいけないのではないでしょうか。限りある地球の中で、ヒトのみの生存や利益だけを考える時代は終わったのではないでしょうか!